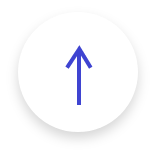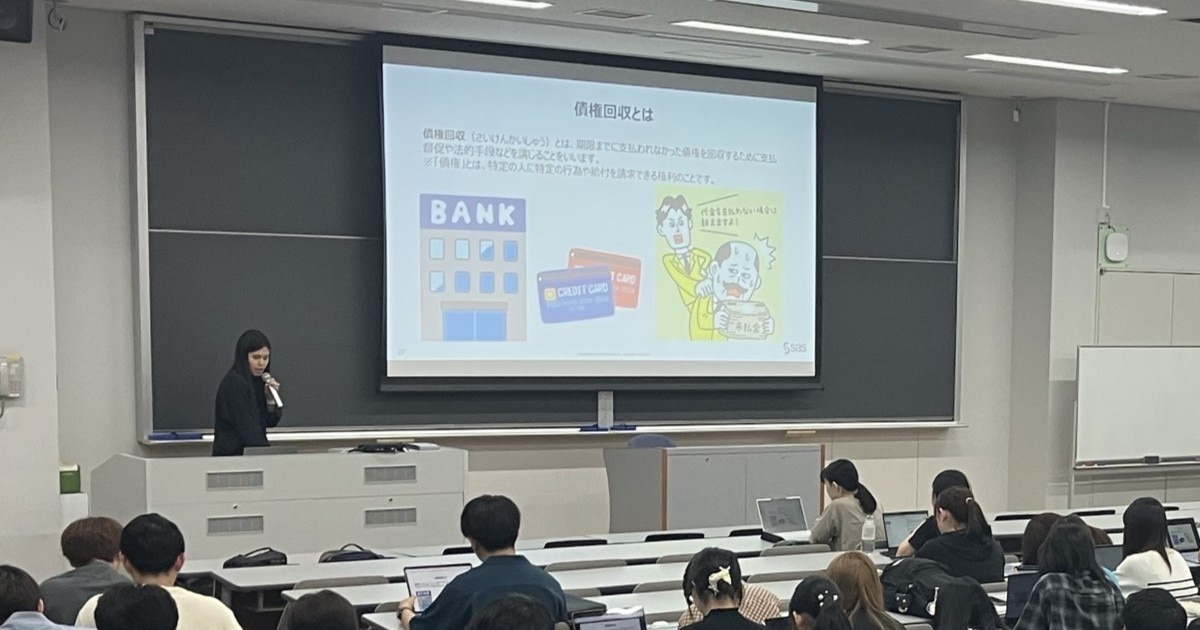
マーケティングにおける「最適化」とは何か?
はじめに
SAS Institute Japan様と共に、同志社大学 京田辺キャンパスにて「マーケティング×最適化」をテーマに講義を行いました。
企業は今、膨大な顧客データを活用できる一方で、施策の選択肢やビジネスルールが増え、運用はより複雑になっています。こうした中、勘や経験に頼る従来の方法では、最適な意思決定が難しくなっています。
本講義では、こうした課題に対し、「最適化」を用いたデータに基づいた意思決定についてお話ししました。
本記事ではその内容をもとに、マーケティング施策をより精度高く実行するためのアプローチをご紹介します。
マーケティングと最適化の接点
マーケティングの目的は、顧客にとっての価値を最大化しつつ、自社の利益を最大化することです。一方、最適化とは、限られたリソースの中で最大の成果を得るための意思決定プロセスです。
現場では、「誰に、どのようなタイミングで、どの施策を打つか?」という問いへの答えが求められますが、多くの場合、それは勘や経験に依存しています。さらに、以下のような制限も考慮する必要があります:
● 予算や人員などのコスト制約
● 顧客接触頻度の制限(例:メール配信は7日に1回までなど)
● その他のビジネスルール
このような複雑な条件の中で意思決定の精度を高めるには、最適化を用いることが効果的です。
機械学習による施策効果の予測
最適化による意思決定を行うには、まず各施策がどの程度の効果をもたらすかを把握する必要があります。このとき活躍するのが、機械学習による効果予測モデルです。
近年の企業は、顧客の属性情報だけでなく、以下のような行動データを蓄積しています:
● Webサイトやアプリの閲覧履歴(例:商品ページの閲覧回数、カート投入の有無)
● 過去のキャンペーンへの反応(例:開封/クリック/購入)
● オフライン購買や来店履歴
こうした時系列性のあるデータを、特徴量(説明変数)として加工・設計することで、顧客のリアルタイムな動向をとらえることができます。
また「施策配信後数日以内の購買有無」や「施策クリック率」などを目的変数(予測したい対象)とすることで、次のようなモデルを構築することができます。
● クーポン配信を打った場合、購買率は何%になるか
● メール配信の開封率はどれくらいか
● 定期施策を打った場合のCV(コンバージョン)はどう変化するか
このようなモデルを作成することで、実際に何万人という顧客に対して施策を実施する前に各施策で期待できる効果を見積もることが可能になります。
最適化の導入
しかしながら、各施策の効果を見積もったとしても、次のような制約が存在します:
● 同じ日に施策を打てる人数には限りがある
● 特定施策は特定期間にしか実施できない
● ある顧客には直近7日以内に既に施策が届いている
さらには、チャネル・施策の多様化なども相まって、人力で最適なアプローチを導き出すのは困難です。
このような複雑な状況を踏まえた上で、「どの顧客に、どの施策を、いつ打つべきか?」を決める必要があります。ここで活躍するのが最適化です。
最適化とは、目的関数(最大化・最小化したい成果)を定義し、様々な制約条件のもとで最適な意思決定を導き出す数理的な手法です。
最適化では、次のような要素を設定する必要があります:
● 目的関数:「全体のCV数を最大化する」「売上を最大化する」など
● 制約条件:業務上の要件(例:3日に1回以上接触しない、配信枠は1日3万人までなど)
これらを最適化の形に落とし込むことで、複雑な施策の組み合わせを、合理的に選ぶことが可能になります。
最適化のための業務要件整理
現場で最適化を適用するためには、業務要件を最適化モデルに落とし込む必要があります。
このプロセスこそが、技術と現場をつなぐ最初のハードルであり、最適化の成否を左右する重要なステップです。
1. 目的関数の定義:何を最適化するのか
最初に定めるべきは、最適化の「目的関数」です。これは、数理的に最大化・最小化したい指標に相当します。マーケティング施策においては、以下のような目的が想定されます:
● CV数の最大化
● 売上の最大化
● コストの最小化
目的を明確に定義することで、以降のモデル構造がぶれずに設計可能になります。
2. 最適化対象の定義:何を選択肢として扱うのか
次に最適化対象の定義を考える必要があります。つまり、どんな選択肢の中で最適化するのかという点です。
● どのような打ち手があるのか
● どのようなタイミングを取りうるのか
● どの施策を適用するのか など
3. 制約条件の定義:実務上の制限を反映
最後に制約条件を考えます。たとえば以下のような要件を、制約条件として設定します:
● 接触頻度の上限:同じ顧客に連続でアプローチしない
● 施策ごとのコスト制限:割引クーポンの配布数制限など
● チャンネル選択の制約:Webの閲覧が多い人にはSMSでアプローチするなど
このような制約を丁寧に整理し、数式またはルールとしてモデルに組み込むことで、現実に即した最適解を導くことができます。
こうした要件定義は、現場のビジネスルールを数理モデルに翻訳する作業でもあり、最適化プロジェクトの重要な作業です。
まとめ
マーケティングの現場では、直感だけでは最適な施策選択が難しい局面が多く存在します。
しかし、機械学習を用いた効果予測と、数理最適化を用いることで、データに基づいた意思決定を行うことが可能になります。
CNSについて
CNSではAIをビジネスに活用するコンサルティング、AIを活用したデータ分析・データ利活用などを支援しています。
AIの活用にご興味のある方は、お気軽にご相談下さい。